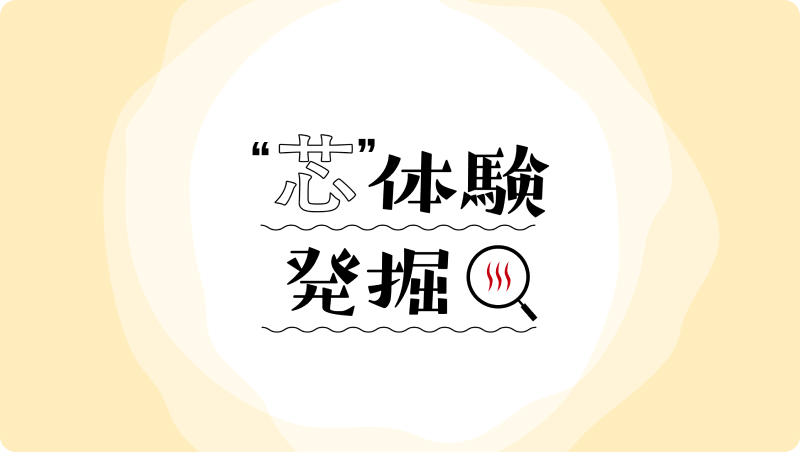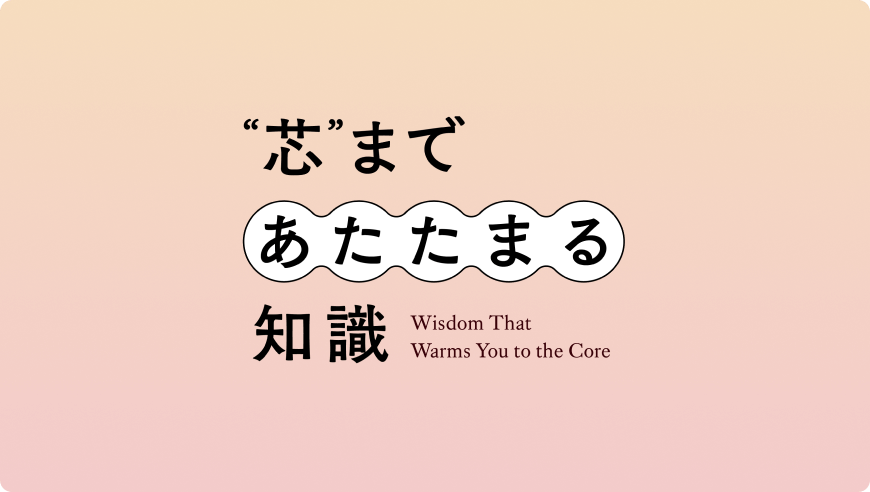「銭湯代行業」の看板を掲げ、町の銭湯や日帰り温泉施設の再生を手掛けるニコニコ温泉。現在までに計5施設を引き継ぎ、運営しています。

【ニコニコ温泉が引き継いだ温浴施設】(2025年3月時点)
富士見湯(東京都昭島市)
東京浴場(品川区)
湊山温泉(神戸市)
辰巳温泉(大阪市)
桑の湯(長野県塩尻市)
それらの銭湯を覗いてみると、ロビーには数千冊の漫画が並び、空間を立体的に使った休憩スペースなど既存の銭湯とはかなり違った雰囲気。古き良き銭湯のイメージを残しながら、様々な年齢層が楽しめる「ニコニコ流改装」が随所に見られ、遊び心にあふれています。そして、早朝から深夜までと、営業時間が長いのもニコニコ温泉各店の共通点。なかには、オールナイト営業の店舗も。
さらにどこのお店も、スタッフが生き生きと働いている姿がとても印象的なのです。

こう書くと、減りゆく町の銭湯を次々と再生させる、一本筋の通った硬派な会社と思う方も多いでしょう。
しかし、ホームページを見ると、ユルいアニメキャラクターが並び、会社組織の欄には「くノ一(くのいち)事業部」「コスプレ・モデル事業部」と、とても銭湯再生企業とは思えないような部署が並んでいます。ウワサではニコニコ流銭湯経営術が記された「奥義書」が存在するという話も。まじめなのか、ふざけているのか……よく分かりません。

このちょっと謎めいたニコニコ温泉という会社は、どんな人がはじめ、なぜ銭湯の再生事業を手掛けているのでしょう。 そしてこの先どこを目指しているのでしょうか。
そんな疑問を解明するために、ニコニコ温泉が引き継いだ日帰り温泉施設、神戸の湊山温泉で、代表取締役の真神友太郎さんにお話を伺いました。
(疑ってゴメンナサイ。懐の広いとても魅力的な会社でした)
(プロフィール)
真神 友太郎(まがみ ゆうたろう)
1972年広島市生まれ。ニコニコ温泉株式会社代表取締役社長。大学卒業後、ゼネコンに就職。工事前の地盤調査に携わる。その後、いくつかの職を経験したあと、船井総合研究所に入社。温浴コンサルタントとして15年勤務したのち、ニコニコ温泉を立ち上げ現在に至る。
コンサルタントとして引き継ぎ先を探していたら、自分が銭湯をやることに

2015年、経営難により閉鎖が決まっていた「湊山温泉」に救世主が現れて、営業を継続するというニュースが関西では大々的に流れました。真神さんが湊山温泉を引き継がれた経緯を教えていただけますか?
当時、私は船井総合研究所(※)(以下、船井総研)の温浴チームに所属するコンサルタントだったんです。経営不振の温泉施設やスーパー銭湯の建て直しが主な仕事でしたが、物件の引き継ぎ先を探すのも仕事のひとつで、湊山温泉(※)も、とある企業が手を挙げてくださっていたんです。
※船井総合研究所:経営コンサルティング会社。温浴施設のコンサルティングも行う。
※湊山温泉:神戸市兵庫区の平野温泉郷に湧く天然温泉を使った日帰り温泉施設。平野温泉郷の歴史は古く、平安時代に平清盛が湯治に訪れたという伝説も残っている。
ところが、ちょうど仕事をやめて少しのんびりしようかなと思っていたところ、引き継ぐ予定だった企業の社長さんから 「えっ、辞めるの? 辞めるんだったらあなたやってよ」って言われて、私が引き継ぐことになりました。
いやいや、そんな簡単に決めちゃって大丈夫だったんですか!?
その社長さんの前で、なんかポロッと言っちゃったんですよね。「やっぱり銭湯って面白いから、自分でやりたいなあ」って。
そういう成り行きでしたから、最初は「やることになったけど、俺は一体どうするんだ。なんにも考えてなかったぞ」って感じでした。
ほぼ同時期に、富士見湯も同じような感じで引き継ぐことになって、2015年にニコニコ温泉株式会社を立ち上げました。

ポロッと口走ってしまったんですね(笑)。真神さんに「自分で銭湯をやりたい」と言わしめたものはなんだったんですか?
うーん、なんで実行しないの!? という、もどかしさですかね。この銭湯はオールナイト営業にしたら絶対黒字になるだろうなとか、町なかのあの銭湯は駐車場を1台増やしたら月に5万円ぐらい売り上げが増えるのになとか。そういう計算は得意だったので、経営不振の銭湯でも、伸びる余地がまだまだあるなと思っていたんです。
コンサルという立場で温浴施設にそういった提案はされていたと思いますが、なかなか実現しなかったのはなぜですか?
銭湯にオールナイト営業を提案しても、自分自身の作業負担や人件費のことが真っ先に頭に浮かんでやらないんです。
でも、僕はまれにオールナイト営業している施設の社長さんに話を聞きに行ったり、駐車場に一晩中張り付いて客数や客層のデータを取ったりしていたので、いけるなという確信を持っていました。
オールナイトや長時間営業は、今やニコニコ温泉さんの勝利の方程式のひとつになっていますよね。
都市部でやらない手はないですね。ただし、家族とアルバイト数人程度の形態から脱却しないと実現しないので、組織づくりが重要になってきます。あと、軌道に乗るまではどうしても人件費などの固定費が大きくなるので、一時的には赤字になります。
オーナーさんの負担を考えると、そこまで無理しなくていいやという気持ちになるのかもしれないですね。
でも、そこを一歩踏み出せば、オールナイト営業は広い客層に来てもらえるメリットがあるんです。早朝4時〜5時台には、おじいちゃんおばあちゃんが来てくれますし、特に週末の深夜の時間帯は若者が驚くほど来ます。
閉店時間が早く、昼間働いている現役世代には利用しにくかった銭湯が、オールナイト営業にすると客数が倍ぐらいになるんです。
基本的に今ニコニコ温泉でやっていることは、私が船井総研のコンサル時代に実践していたことがベースになっていますね。
スタートダッシュは成功したけれどこれからどうする。地方銭湯・桑の湯の挑戦

引き継がれた長野県塩尻市の「桑の湯」が、2024年12月30日にリニューアルオープンしました。ニコニコ温泉では初めての地方店舗になりますが、早朝5時に開店して深夜1時まで営業(13時~15時は一旦閉店)するなど、かなり攻めた運営です。長くやっていけるのかなと、こちらが心配になります。
*桑の湯・・・長野県塩尻市で唯一残っている町の銭湯。創業は昭和4(1929)年という老舗。今まで経営していた創業家が2024年6月に体力的な理由から閉業。後継者を公募し、複数の応募の中からニコニコ温泉が選ばれた。
塩尻市で唯一残った昔ながらの銭湯だったということもあり、ニコニコ温泉が引き継ぐことが決まると、地元のマスコミが、まるで白馬に乗った王子様が現れたかのように大々的に取り上げてくれたんです。そのお陰もあって、初日には700人ぐらいのお客さんが来てくださいました。
ニコニコ温泉には銭湯経営術をまとめた“奥義書”があるんですけど「初陣炸裂法」でスタートダッシュは成功した感じですね。でもお正月以降は、もう客足は落ち着いてきています。

「初陣炸裂法」って……。そういう奥義書は実在するんですね(笑)。
悪いところはとりあえず目をつぶって長所を伸ばす「長所伸展法」とか、正月とゴールデンウィーク、お盆は意地でも前年越えをする「年間3ヶ所前年超え法」とか、奥義はいっぱいありますよ(笑)。毎年、スタッフで合宿をするんですけど、その時は奥義書をみんなでおさらいします。
奥義も深掘りしたいのですが、また別の機会に譲って……。桑の湯はロビーも大きく改装されましたし、アルバイトスタッフもたくさん雇われました。しばらくは赤字覚悟ですか?
そうですね、1年ぐらいはお金が溶けていく覚悟をしています。この1年は死に物ぐるいで収益が出る体制を整える時期になると思います。
銭湯を引き継ぐときには徒歩商圏の人口を調べるのですが、桑の湯の場合、東京浴場と比べると10分の1、湊山温泉だと7分の1ぐらいしか人が住んでないんですよね。さらに、この先5年もかからずに5%程度の人口が減るという予測もあります。
売り上げ規模にしても、入浴料収入の見込みは2000万円程度で、都市部で出店する際の目安にしている金額の3分の1ぐらいしかありません。
普通に計算すると、ずーっと赤字が続くので、今までだったらやらなかった物件です。

そこまで予測できているのに、なぜ引き継ごうと思われたのですか?
ずっと、ニコニコ温泉で地方の銭湯を存続させることに挑戦したいと思っていたんです。都市部だったら、あんまり変なことをしない限り経営が軌道に乗ることはもう実証されていますし、ほかにも銭湯をやりたい人がちょくちょく出てきますしね。
桑の湯でこの先30年、設備投資もしながら運営できる仕組みをつくることができれば、 日本全国、銭湯を残せる場所が無限に広がりますから。
それと会社の組織が充実してきた部分も大きいですね。うちの門を叩いて入社した20代、30代の若い社員たちが、ニコニコ温泉のノウハウを吸収して、今度は自分自身のアイデアをどんどん形にする段階に入ったと思っています。彼らは、とにかく新しいことをやりたがるんです。むしろ僕が止める側にならないと、勝手に企画が進んでいってしまうぐらいで(笑)。

桑の湯の立ち上げの責任者の相良さんは26歳とのことですが、ニコニコ温泉は人の育つ早さがすごいですね。
うちでは、最初はみんなアルバイトとして店舗の仕事を覚えてもらい、その後店長になったら2年ごとに店を変わるか、キャリアを上げてマネージャーになって新規事業に携わってもらいます。
店長になったら、最低でも仕事時間の3分の1は店を離れて、いろいろなところに出張するように言っています。半分以上、出張している店長もいますね。
それは人気の温浴施設や関連した場所を見に行くためですか?
いや、温浴施設に限りません。むしろ、銭湯を蘇らそうと思ったときに必要なヒントや情報って、銭湯のなかにはないんですよね。どちらかというと、外にあるんです。
だから、急成長している商売や、新しい技術を積極的に導入しているチェーン店、どこでもいいんですけど、自分でアンテナを張って、出張後にレポートを上げてもらっています。レポートを書かなきゃ出張費は出さないよって言って(笑)。
ニコニコ温泉の店長やマネージャーさんたちが、生き生きと動き回っている理由が分かったような気がします。
孤独や暇と闘っている現代人にとって銭湯は絶対にあったほうがいい

銭湯を再生させたり、地方の銭湯を残そうとしたりされている原動力みたいな部分をお聞きできればと思います。
銭湯が日本中に残ったらいいなというのは、いろいろな場面に立ち会ってきた中で実感しています。自分でニコニコ温泉を立ち上げてからは、ますます「これは残さなきゃダメだな」と感じています。
特にどういう部分で「残さなきゃ」と感じておられるんですか?
20代の頃に、短い期間ですが環境NGOで働いたり、インドやアジアを旅したりした経験から導いた答えなのかもしれませんが……日本って、餓死する人も凍死する人も、自分が見てきた国と比べると、明らかに少ないんです。言い換えれば、死と直結した生活を しなくていいから、社会のなかで誰かと協力しなくても生きていけるんですよね。一人で生きていける国には、自然と孤独や暇が生 まれてくる。
その孤独と暇にどう対処するかという問題は、現代においてかなり大事で、SNSがあれだけ流行るのも、 孤独や暇を解決するためだという気がしています。
銭湯はそういう孤独や暇、メリハリのない生活を、微力ながら解消するのにすごく役だっているなと思うんですよね。
なるほど。銭湯を通した現代社会の深い洞察ですね。
うちの銭湯では、年末になるとロビーに1メートルぐらいある鐘を吊して、お寺でもないのにお客さんに「除夜の鐘」をついてもらったり、「なんなんですか!それ」っていうイベントをいろいろ企画しています。そんな風に、銭湯って真面目な要素を残しつつ、 バカバカしく思えることがどんどん出来る空間なんですよね。
そこでは、普段会話しないお客さんが、スタッフや偶然そこに居合わせたほかのお客さんと言葉を交わしたり、風呂屋らしいコミュニケーションが生まれるんです。こういうのってけっこう銭湯独特で、傍から見たらどうってことない風景かもしれないですけ ど、ちゃんと社会課題に対応してるなって思います。

もしかしてホームページのユルい感じも、そういった狙いがあるんですか?
僕は、堅苦しかったり、息苦しかったりするのがホントに苦手なんです。ホームページのあの雰囲気に関しては、いろいろな意見がありますけどね。
あとは、コンサル時代にコスプレイベントを開催していた温泉旅館があるのですが、目当てのコスプレイヤーに会うために、遠方から新幹線に乗って来る方もいて。サブカルチャーが人やお金を引っ張ってくる力を目の当たりにしていたんですよ。
基本的にお金が枯渇しない限りは、できることはなんでもやればいいという考えなので、漫画やコスプレ、ゲームなどの情報発信力や魅力は、銭湯にも取り込んでいければいいなと思っています。
そういう思いもあって、社員には美術系の学校を卒業した人を一定数採用するようにしています。
これからの10年、プレーヤーを増やすために必要なこと。その秘策とは

最近10年を振り返ると、京都のゆとなみ社(※)のような銭湯継業集団や、各地でも銭湯を引き継ぐ若い人が登場してきました。真神さんは、銭湯の現在地をどのように見ておられますか?
うちもそうですけど、既存の物件を引き継いでいる限りは、軒数は減っていくしかないんですよね。さらに、入浴施設の経営は、資金力や経験値がないと難しい部分も多く、やりたい意欲はあっても、現状誰でも出来る商売ではないんです。
将来的には、銭湯が、資金力や経験値がそれほどなくてもゼロから開業できる個人商売になればいいと思っています。社内では「700万円で開業できる銭湯」をつくろうって話をしています。
※京都市に拠点を置く銭湯継業専門集団。2015年に当時24歳だった代表の湊三次郎さんが「サウナの梅湯」を引き継いだのを皮切りに、2024年までに11軒(うち1軒は独立)の銭湯を継業している。
いま銭湯を新築開業しようと思ったら数億円かかると言われていますが、700万とは桁違いですね。
サウナってプライベートサウナも含め、すごく数が増えたじゃないですか。今はもう誰でも参入できる商売になりました。理由は簡単で、初期投資がすごく安くなったから。
お湯の浴槽はなくても、水風呂とシャワーがあれば大丈夫だということがはっきりしてきましたし、テントサウナを使えば100万円も掛からないんじゃないでしょうかね。
銭湯も、その気になれば700万円程度でつくれるという確信があるんです。10年後は、やりたいと思った人が新たにゼロから立ち上げられるようにしたいし、そうなって欲しいと思いますね。

700万円で開業できれば、自分でやろうというプレーヤーが増えるでしょうね。
いやー、もうめちゃくちゃ銭湯をやりたい人が現れて、業界が活性化すると思います。ある程度「型」ができれば、出資したいという人もでてくるでしょうし、うちの若い連中なんかはすごい勢いでお金を集めてくると思います。
その値段でつくれる何か秘策はあるんですか?
まずは、既存の銭湯の概念を一旦横に置いておきましょう。
たとえば、スーパー銭湯では壺風呂がすごく人気ですけど、一人用のバスタブを並べるだけだったら、1個数万円として、10個並べても100万以内に収まりますよね。
現状は床に埋まっている配管も、耐熱ホースで代用できるかもしれない。ポンプだって、熱帯魚の水槽に使う大きめのポンプがあれば、バスタブのお湯ぐらい循環できるんです。現状のスペックはいらないよねっていう設備が結構あるんですよね。
そういう手づくり感あふれる、秘密基地の延長線上のようなおふろなら、700万で可能なんじゃないかという思いがあります。
まあ、10年後には私はもう60代になっていますし、実際に動くのは今の20代、30代の若いマネージャーが中心になるでしょうけど、なんとか実現させたいですね。

以前から真神さんのことは知っていましたが、直接お会いするのは今回が初めて。どんな方かとても楽しみでした。
実際にお会いした感想は、緻密な計算に裏打ちされた「ニコニコ流奥義」を駆使して、世に銭湯を残す仕事人でした。
ぶしつけな「やっていけてるんですか?」という質問にも、実際の数字を挙げながらきさくに答えてくださる、心の広い社長さんでした。ありがとうございました。
みなさんもニコニコ温泉の運営する銭湯に一度行ってみてください。地元の人たちに愛される各地の銭湯を見れば、「社会をあっためる」ってこういうことなんだなと伝わってくると思います。
銭湯の未来を既成概念にとらわれない工夫で切り開こうとする真神さんのインタビュー、いかがでしたか? 未来をよりよくするためには、今日の自分をよくすることから。松田医薬品の入浴剤で、一日の身体のケアをしてみませんか?

刻み草果にバスソルト/ラベンダー&オレンジ