「ヤマザキさん、100年後のおふろはどうなると思いますか?」
マンガ『テルマエ・ロマエ』のなかで、古代ローマのおふろを描いてきたヤマザキマリさんに、今回あえて「未来のおふろ」について聞いてみました。
「風呂キャンセル界隈」なんて言葉も多く耳にする今。
おふろを愛する者として、入浴文化を絶やしたくない。でも、高齢化や燃料費の高騰で閉業する銭湯が相次いだり、気候変動などによる海外での水不足のニュースを目にしたり。 たっぷりのお湯を沸かしてゆっくりあったまる、昔から当たり前にあったおふろはこの先どうなっていくのか? と不安になる時もあります。
そんな思いで、ヤマザキさんに冒頭の質問をしてみました。
すると、世界各国のおふろに入り、入浴文化の歴史にも明るいヤマザキさんからは意外な返答が。
並々ならぬおふろ愛で『テルマエ・ロマエ』を執筆し続けるヤマザキマリさんと、長年、素材にこだわった生薬の入浴剤をつくり続ける老舗メーカー、松田医薬品 松田憲明の対談をお届けします。

(プロフィール)
ヤマザキマリ
漫画家・文筆家・画家。
1967年東京生まれ。84年にイタリアに渡り、フィレンツェの国立アカデミア美術学院で美術史・油絵を専攻。比較文学研究者のイタリア人との結婚を機にエジプト、シリア、ポルトガル、アメリカなどの国々に暮らす。2010年『テルマエ・ロマエ』でマンガ大賞2010受賞、第14回手塚治虫文化賞短編賞受賞。著書に『ヴィオラ母さん』『ムスコ物語』『歩きながら考える』『扉の向う側』『貧乏ピッツァ』など。現在、『続テルマエ・ロマエ』を集英社「少年ジャンプ+」で連載中、2巻が好評発売中。

(プロフィール)
松田憲明
松田医薬品株式会社 専務取締役 営業本部長。
立教大学を卒業後、2014年にアルフレッサ株式会社に入社。2017年にアルフレッサ ヘルスケア(株)経営企画部へ入社。2019年に家業である松田医薬品株式会社に入社。2025年5月より現職。
『テルマエ・ロマエ』はおふろへの渇望から生まれた⁉︎

松田:ヤマザキマリさんの代表作である、マンガ『テルマエ・ロマエ』は、「おふろ×歴史×タイムスリップ」という斬新な発想の作品です。どうしておふろをテーマにマンガを描こうと思ったんでしょうか?
ヤマザキ:連載がスタートしたころ、私はポルトガルにいて、湯船のない家に暮らしていました。家ではシャワーだけだし、日本のように街に銭湯や温泉があるわけでもない。 「おふろに入りたい! なのに入れない!!」という、入浴に対しての枯渇感が臨界点まで達していた時期です。
それで編み出したのが、おふろに入っている人の絵を描くことで自分もお湯に浸かっているような気分になるという技です。入浴している人を描くことが一種のストレス解消法になっていました。そして、その延長線上で生まれたのが『テルマエ・ロマエ』です。最初から「何か面白い漫画を生み出そう!」と思って描いたものではなくて、募りに募ったストレスとおふろへの欲求でできた作品です。
松田:最初からヒットを狙っていたわけではなかった。
ヤマザキ:全然狙っていないです。漫画家として大成しようなんて思ったこともないです。ラッキーだったのは、『テルマエ・ロマエ』を拾ってくれた出版社の編集者も大のおふろ好きだったこと。「俺たちが面白ければいいよね!」っていう、同人誌みたいなノリで連載がはじまっちゃったんですね。
だから『テルマエ・ロマエ』がどうしてあんなにヒットしたのか、今でもよくわからないです。当時は海外にいて、SNSも今ほど普及していなかったので、日本での反響もリアルタイムでは見られませんでしたし。
松田:では、おふろの魅力を多くの人に伝えたいというメッセージ性も特になく?
ヤマザキ:まったくありません。古代ローマ人が日本の銭湯に来たらすごくおかしいだろうな、実際古代ローマ人が今もいたら、日本の温泉は大人気な渡航先になっていただろうな、 などと思って、黙々と描いていました。古代ローマ人が日本の昭和の銭湯から現れる絵を描いて、ファックスで日本の漫画家の友人に送ったら「マリ、そんなにおふろに入りたいなら帰国したら。頭大丈夫?」って心配されました(笑)。
「おふろ」は、文化であり哲学だった
松田:ヤマザキさんはイタリア、ポルトガル、シリアなどなど、いろいろな国に住んだ経験をお持ちだと思いますが、各国のおふろ文化の違いに驚いたことはありましたか?
ヤマザキ:入り方が違うというレベルではなく、おふろの“概念”がまるで違うんですね。海外のホテルには浴槽がない部屋も多いし、あっても湯をためてそのなかで体も洗うという、いわば「汚れたお湯に浸かる」状態になりますよね。
いっぽう、日本のお風呂は、まず体を洗って清めてから入浴する。つまり、禊(みそぎ)のように精神面を浄化させる目的があります。
松田:おふろに入る「目的」が違うんですね。
ヤマザキ:ところが、古代ローマには日本に近い入浴文化があったんです。
正確には、まず最初に運動をして代謝を高め、それから体にオイルを塗り、「ストリジル」という金属のヘラのようなもので肌の汚れを落とす。その後に水浴び、温浴、蒸気浴と段階を踏んでいく。
松田:かなり細かくやることが決まっているんですね。
ヤマザキ:こうしたシステムは、心身双方の健康を保つためには運動や入浴が重要だという、古代ローマ、古代ギリシャの哲学に由来しています。

松田:そういった古代ローマの入浴法が、バスタブで身体を洗う現代のスタイルに変化していったのはなぜなんでしょうか?
ヤマザキ:古代ローマの段階式入浴法は、相当大きな浴場でないと実現できないというシンプルな理由からだと思います。
イタリアはなぜ日本のように豊かな浴場文化が残らなかったのか? ともよく聞かれるのですが、これは古代ローマの歴史ととてもシンクロしています。領土が拡張していくと、どうしても戦争は発生してしまいます。古代ローマもまさに類に漏れず。敵国はまず相手国のインフラを破壊して国の機能を弱体化させるわけですが、水の供給が絶たれると、当然おふろも沸かせなくなります。
また、紀元1世紀頃からキリスト教が広まり「裸で人前に出るのは恥ずべきことだ」といった倫理が根付きました。これらの要素が絡みあって、古代ローマにおける浴場文化は廃れていったのだと考えられています。
松田:逆に、日本のおふろ文化に近い国はありましたか?
ヤマザキ:特にアジアには、日本人をきっかけにして発展してきた浴場がたくさんあるんですよ。
たとえば台湾の北投(ベイトウ)温泉は、1894年にドイツの地質学者が発見したのち、大阪の商人が整備した温泉街。たぶん、ドイツ人が見つけただけではそんな発展の仕方はしないはず。日本人が手を加えたことによって、温泉地として発展したんですね。
あとは、第二次世界大戦中、日本軍が海外に遠征した際まず確かめることのひとつに、「温泉が沸いているかどうか」があったそうです。温泉が沸いていたら、そこを軍の療養場としてしつらえる。他の国の人たちは、なかなかそこまでしないですよ。
松田:日本人って、それくらいおふろ好きなんですね。
ヤマザキ:日本では災害時に自衛隊が野外入浴セットを設置するじゃないですか。効率だけ考えればシャワーのほうがいいのに、被災地をわざわざおふろで支援するなんて、世界でも日本だけです。おふろがただ単に衛生のためだけではなく、心を癒すためにとても重要なものだと考えられている象徴的なエピソードだと思います。
未来のおふろはどうなるの?
松田:『テルマエ・ロマエ』は古代ローマの時代のおふろの話ですが、今回は「未来のおふろがどうなるか」についてもお聞きしたいと思っています。100年後、私たちが入るおふろはどうなっていると思いますか?
ヤマザキ:それは、まさに『テルマエ・ロマエ』に答えが描かれています。
ルシウスは古代ローマ時代から現代の日本にタイムスリップして来て、ケロリンの桶やシャンプーハットなどに驚きますが、自分がいるのが浴場だということはすぐに理解できた。要するに、数千年の時を超えても、おふろの基本的なスタイルは変わっていなかったんです。
もちろん、技術が発展したことで、土地が限られているところでも使える簡易型のおふろや、お湯を循環させるような数々の新しい機構は発明されました。そういった便利な機能はこれからもきっと増えていく。だけど、地球が水の星である限り、湯に身体を浸けてあったまるというおふろの原則は、ずっと変わらないと思います。

松田:数千年経っても、おふろの形は変わらない。
ヤマザキ:ただ、例えば、温泉に行けない際に、温泉気分が味わえる装置とかがあったらおもしろいだろうなとは思いますね。
『ドラえもん』で、「シネラマン」という、錠剤を飲むと家の小さなおふろでも広々とした温泉に入っているような気分になれるというひみつ道具がありました。あれはすごく羨ましかったですね。薬ではなく、VRメガネなどでもできそうじゃないですか? 実現したら欲しいです(笑)。おふろというよりは、VRなど別の技術の進化ですが。
松田:VRゴーグルと入浴剤を合わせれば、家で温泉気分になるのも夢じゃないかもしれませんね。

ヤマザキ:温泉好きの人って、ペラペラのせんべい布団で寝るような、ひなびた温泉旅館でも、いい泉質の温泉だったら行きたくなるじゃないですか。逆に、近代的でぴかぴかの建物できちんとしていても、加水循環の温泉だったりすると、それほどそそられなかったりする。
おふろの“外側”をいろいろと発展させていっても、最終的には「泉質」が勝つんだと思うんですよ。今までもそうだったように、この先もそうした方向性は変わらないと思います。
松田:たしかに、どんなに未来的なおふろでも、お湯の質がよくなかったら入りたくないかもしれません。
ヤマザキ:そう。だから、私は未来的なおふろに発展させていく方法を考えるより、いいおふろをどう存続させていくかを考えたいですね。『テルマエ・ロマエ』にも登場させた素晴らしい入浴施設が、コロナの時期にいくつか閉業しています。いいおふろ屋さんがなくなってしまうのは悲しいですから。
おふろはなくてはならない心の栄養素

ヤマザキ:最近では「風呂キャンセル界隈(風呂キャン)」という言葉もあるみたいですけど、おふろの魅力を知れば自然と入浴する習慣がつく人も多いんじゃないかなと思っていて。
松田:身体があったまると、いいことがたくさんありますからね。睡眠の質がよくなったり、肩こりが解消されたり、心がゆるんで笑顔になれたり。たくさんの方におふろのよさを知ってもらうために私たちができるのは、いい入浴剤をつくることなのかなと思っています。
ヤマザキ:海外ではそもそもお風呂に浸かる文化が少ないんですね。ヨーロッパの古い石造りの建物は冬になると本当に冷えるんですよ。でも、うちの家族もほとんどシャワーで済ませてしまう。彼らには「お湯に浸かることで芯から温まり、英気を養う」という考えがないんです。
松田:「芯まであったまる」を経験したことがないと、そこへの欲求もそもそも生まれない。おもしろいですね。
ヤマザキ:イタリアにいると「なんでそんなに風呂に入るの?」ってよく聞かれるんです。でも私にとっては、生まれたときから当たり前の習慣。シャワーでは身体はなかなか芯から温まりませんから。
ただおもしろいのは、うちの夫も以前はシャワー派だったのが、今では「おふろに入ると身体の調子がいい」と言って、入浴剤を切らすと「送って」って連絡してくるんです。完全に“開眼”しましたね。
松田:(笑)。おふろに入ると「気持ちがいい」と感じるのは、人間の本能なんでしょうかね。
ヤマザキ:カピバラや猿が、お湯に入ってうっとりした顔をしている映像を見たこと、ありませんか? お湯に浸かると筋肉の緊張がゆるんで心もリラックスするというのは、人間だけじゃなく動物の本能的な反応だと思います。うちの猫も、おふろには入らないんだけど、お湯の溜まった浴槽のフタの上に寝そべって、蒸気の中で寛いでいます。
古代から、各地で「お湯に入るとなんだか元気になる」と気づいて、温泉を愛でていた人や動物がいた。入浴は、生き物にとって普遍的な癒しの行為なんだと思います。温泉は地球の恩恵ですね。
松田:『テルマエ・ロマエ』で描かれている人たちも、みんな本当にゆるんだいい表情をしていますもんね。
ヤマザキ:ローマの浴場のおもしろいところは、皇帝も奴隷もみんな裸になって一緒のおふろに入ること。入浴している時だけは身分の差が消えるんです。地位を表す服や装飾が取り払われて、ただの人間として同じお湯に浸かる。どんな身分の人でも、おふろの前では平等になる。「みんながおふろに入って癒されるのは、あたりまえのことだね」と捉えていた寛大な社会だったようです。そうやって、おふろに入りたいと思う気持ちをリスペクトし合うところは本当に素晴らしいなと思いますね。
松田:最後にお聞きしたいのですが、ヤマザキマリさんにとって「おふろ」とは?
ヤマザキ:幼少期から、おふろに関する大切な記憶がたくさんあります。祖父母と通った銭湯や、母に連れられて行った北海道の温泉。あったかい湯気、水の音、ゆるんだ顔の大人たちの表情。おふろに入っている人たちの、あの安寧な空気感に触れるのが大好きだったんです。おふろって、あんまり悪い思い出ができない気がしますよね。今でも、一日のなかの特別な時間です。
2024年の能登半島地震のとき、断水に悩む高齢者施設などを巡回して訪問入浴するサービス「テルマエ・ノト プロジェクト」が発足しました。

その時に「入浴は命の栄養です」というスローガンを掲げたのですが、まさにその通りだと思うんです。おふろはご飯と同じくらい大切な、生きるための栄養素。 疲れた身体も、傷ついた心も、おふろに入ることで癒され、また前向きにものごとを捉えることができる。自分にとってはなくてはならない存在ですね。
今回、ヤマザキマリさんに「100年後のおふろはどうなると思いますか?」と伺ったのは、松田医薬品が100年後も続く入浴剤メーカーでありたいから。
長年、「質」を追求した入浴剤をつくってきた私たちにとって、ヤマザキさんの「景観よりも、最終的には泉質のよい温泉が喜ばれる」という考えは、自分たちの姿勢は間違っていないと裏付けてくれるようでとてもうれしく思いました。
これからも、みなさんのおふろ時間をより充実させる入浴剤をつくっていきます。
最後に、家のおふろに入る際は入浴剤を欠かさないというヤマザキマリさんに、松田医薬品の入浴剤を使った感想をお聞きしました。


生薬煎

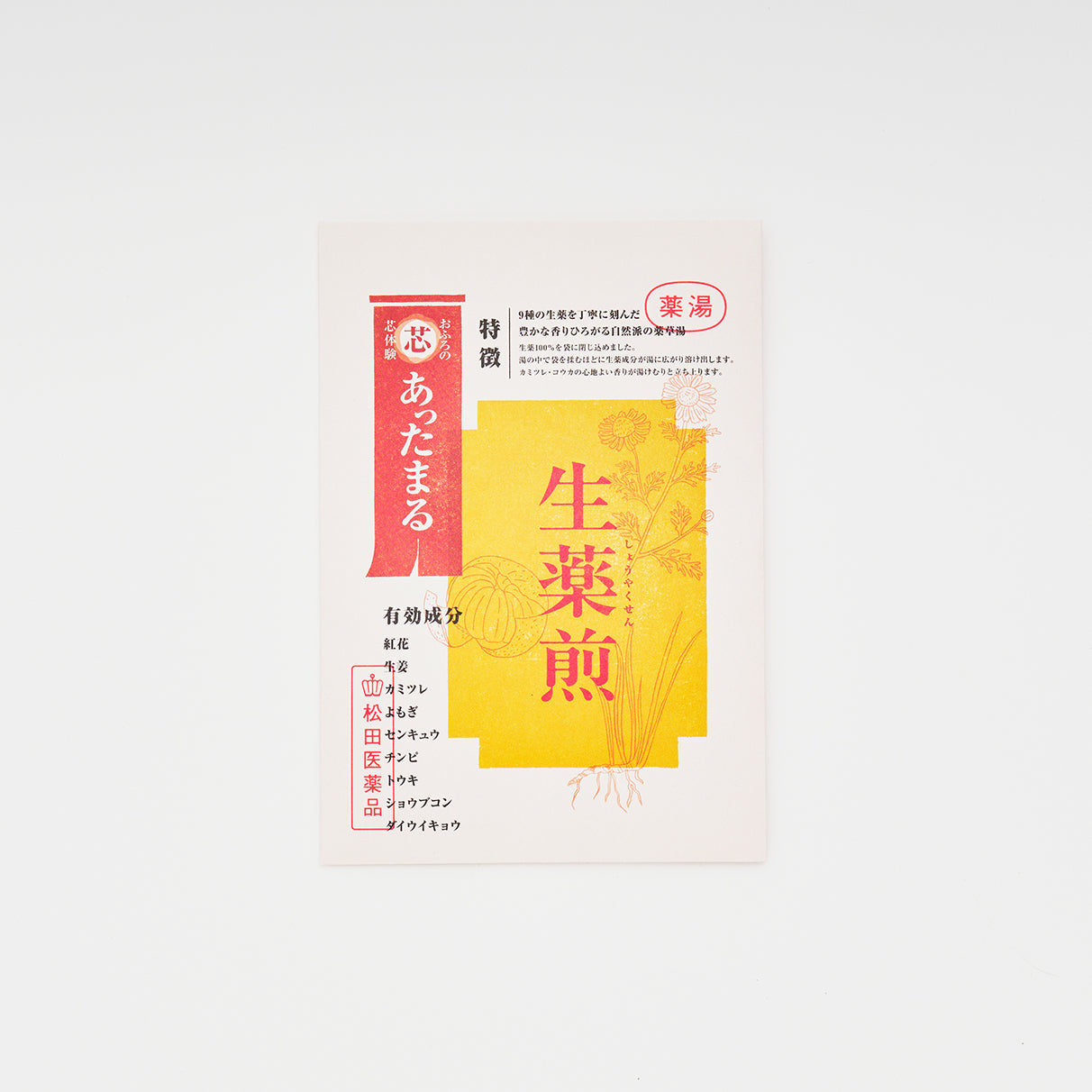
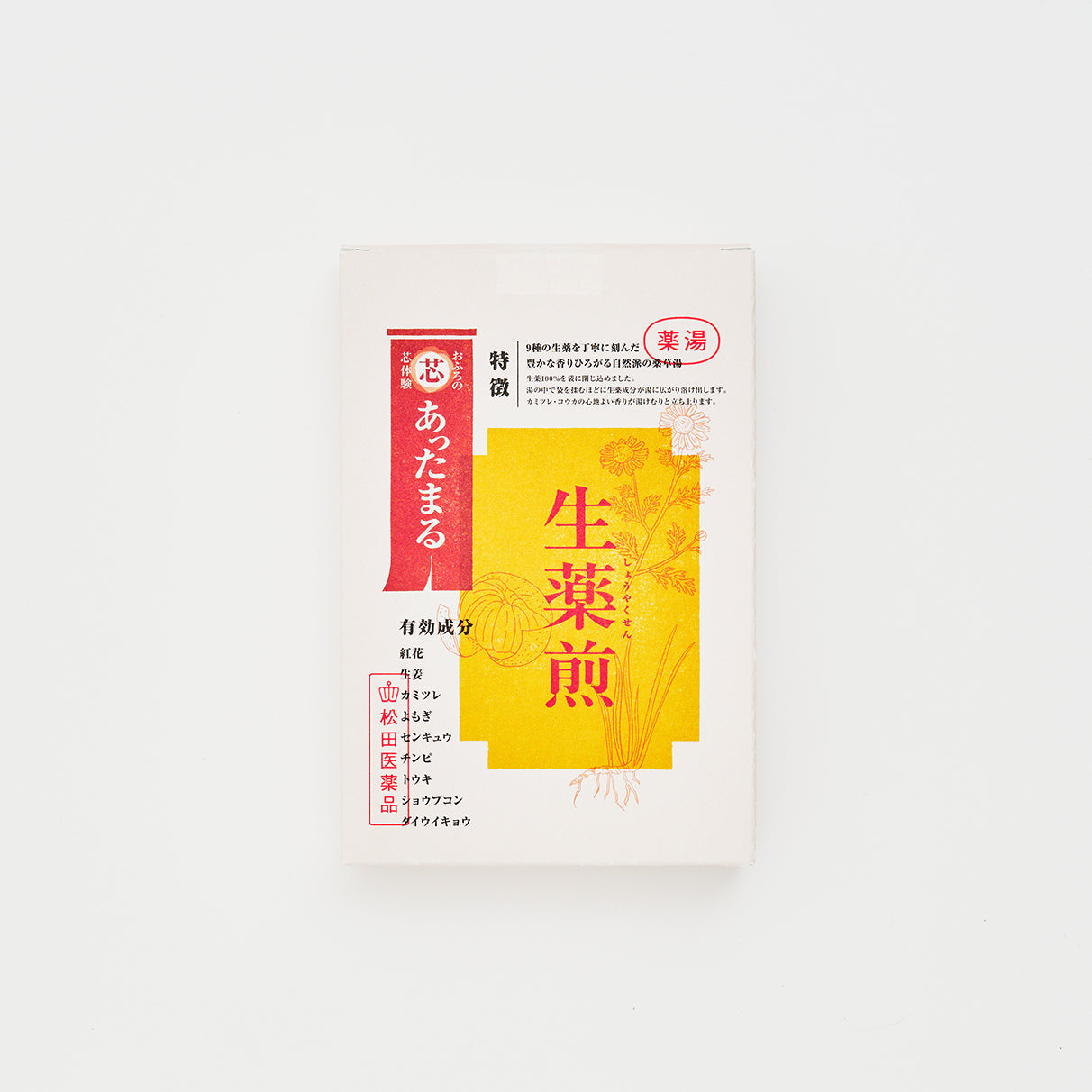

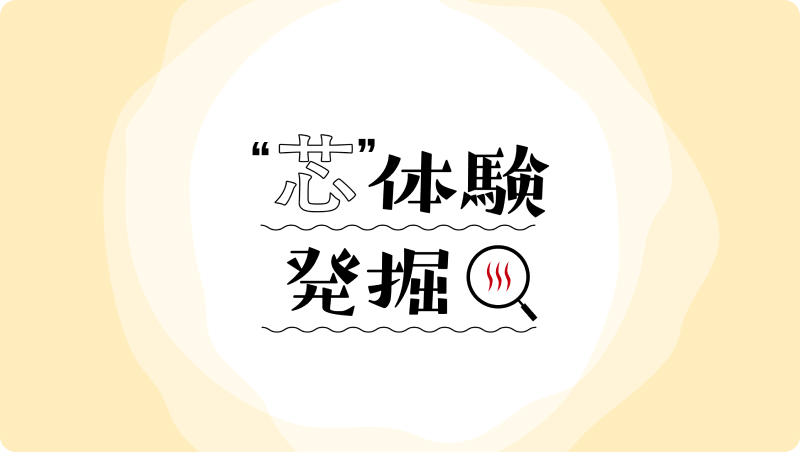
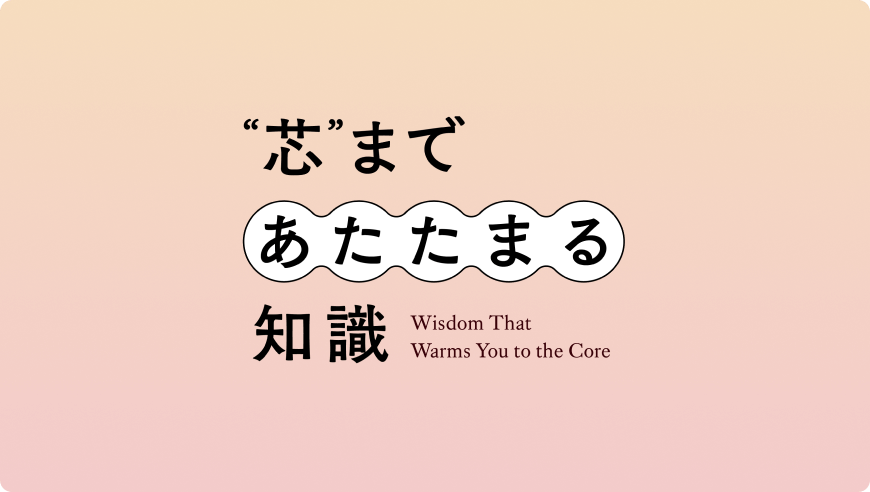
早速使ってみましたが、地球リスペクトな素材が溶けこんだ、大自然から抽出されたハーブティーのようなお湯で体の芯から癒されました。
これは是非ルシウスにも古代ローマで真似してもらいたいですね。